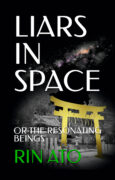AIが発達すると意識を持つのかどうか、私がいくら考えてみてももちろん結論にはたどり着きません。人間の意識についてさえ、それが何なのかよくわからないし。
でも、発達したAIが意識を持つ可能性があるのかどうか、についてはやはり小説を書く中で考え、少し触れています。
所詮フィクションだと割り切って、話の中では勝手なことを色々書いていますが、この意識の部分については考えに考えたあげく、おもしろく書く良い案が浮かばずに思いっきり誤魔化しています。
ただし、書いている途中に思いついたことをスマホにずっとメモし続けていたんですが、AIの意識について書くアイデアに一つ気に入ったものがありました。意識は突き詰めると宇宙に一つしかないというものです。
どういうことかというと、自分以外の他者にも意識があるということを証明するには、自分の意識がその他者の意識を経験してみるしか方法が無い。
しかし、その他者の意識を経験して、自分以外の意識が存在すると確認するためには、その2者の意識が並行して存在していることを認識する別の意識がなければならない。
その場合、結局2者の意識があるのではなく、それを見ている一つの意識の下に2者の意識(のような体験)が含まれてしまっている、ということです。結局その場合も意識は全体で一つしかないという意味です。
この部分を考えていた時のスマホのメモのコピペは次のとおりです。
つまり、より高みの意識が認識する必要があるのよ。それをずっと上に辿って行くと、わたしとあなたは結局いっしょなのよ。一つの意識に集約される。 結局意識は排他的なのよ。排他的なもの(並立を許さないもの)なのに、その一方で何かを認識する意識が存在しているということは、結局なにもかも一つに集約されなければならないということじゃないかしら。つまり、意識の存在を突き詰めて行くと、たった一つの意識に収束するということね。言い換えれば、あなたに意識があるならわたしにも意識があるっていうこと。
これはかなり酔ってますね。酔うと全然ダメになってしまうときと、なんかビビッと勢いよく書いてしまうときと二通りしかありません。
結局、AIに限らず自分以外の他者の意識の存在を知るには、推定あるいは類推によるしかないんじゃないでしょうか。
この考え方は面白かったんですが、こんな風に理屈っぽく書いたらストーリーのバランスが崩れてしまうと思って、ここは思いっきり誤魔化したのは先に書いた通りです。
もう一つ話全体を書く上で、AIの意識の話と関連する点は、前にも書いた身体感覚のことです。あるいは感覚器とかセンサーとか言えば良いでしょうか。
これは自分で勝手に言っていることではなくて、こんな考え方はあるみたいです。
一番簡単に思考実験してみると、仮に自分の脳が事故か病気か何かで、皮膚感覚も含めて外からの情報を一切絶たれた時を思い浮かべた場合、その脳で意識の存在を感じることができるのか、ということ。
さらに、こんなことは考えたくもないが、もし生まれる前からそういう状態に置かれた人がいた時、意識を感じることができるのか?あるいはもっと単純に自分の存在を感じることができるのか?ということです。
他者や世界の存在を感じる方法が全く無いという状態です。
たぶん、意識とか自分の存在を感じることはできないのではないか、と思います。
しかし、仮にそこにほんの一部分、自分の頭の皮膚の感覚が戻り、そこを触られた刺激に対して口の隅っこをほんの少し動かすことができたなら、自分の存在を感じることができるのではないでしょうか。
外からの刺激に対して、なんらかの反応をすることによって、外からの刺激のあり方が変化することを知るという経験をすることによってです。
つまり、意識あるいは自分の存在を感じるということは、自分以外の外との関係性によって生じるという考えです。
それなら、部屋の状況によって動きを変えるお掃除ロボットのルンバにも意識があるということじゃないか、という話になってしまいますが、実はそう考えるのも妥当じゃないかと思えてきました。
前に書いたとおり、他者の意識が存在することを証明することができないのがもし本当ならば、他者に意識が存在しないことを証明する手段も持っていないんじゃないかと思います。
外見的に外界との相互作用で振る舞いに変化を起こしている物体があれば、それは外見的には自分となんら変わりはなく、しかもその物体に意識はないと否定する根拠はありません。
あるいは逆の考え方もできて、人間はルンバと同じようなものに過ぎず、意識なんて大仰に考える意味はない、と考えることもできるかもしれません。
しかし、人間とルンバが大きく違うのは、ルンバは外界からの刺激に対してプログラムされた決まった反応しかしないが、人間の場合はその時々に応じて、異なる反応をするということなのではないか、それは意識を持った自分が判断して反応しているのではないか、という反論があるのではないかと思います。
でもこれには注意が必要で、当然人間の頭脳はルンバよりも大幅に複雑なので、振る舞いがその時々によって異なるように見えるのは当然です。
しかし、人間の頭脳がどんなに複雑であっても、もし完全に同じ条件下であれば、必ず同じ反応をする、というのでは本質的にはプログラムされたルンバと異なるとは言えません。
でも実は、人間や動物は全く同じ条件下でも、異なる振る舞いをすることがあるんだろうと思っています。ただし、それは意識の存在に関わる話ではなく、創造性に関わる問題なんだろうと思います。それはまた別に考えてみたいです。
意識というものの定義にもよりますが、定義を極端に広く捉えた時、極めて低レベルながら、ルンバにもある種の意識があると言うことができるんでしょうか。
将来それがどんどん高性能化されると、意識のレベルが上がっていくということなんでしょうか?もちろん推測、類推ですが。
それとも、意識なんていうものに実体は無く、そこには感覚器を持って、ただ外界と相互に作用をしあう物体があるというだけなんでしょうか?
そういうものは、哲学的ゾンビという名で呼ばれているようです。